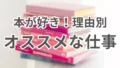日々のストレスと戦う中で、「強くなりたいな」と願う人は多いのではないかと思います。
私も、心が強い方ではないので、揺らがない心を持ちたい、ストレスに強くなりたい、と色々と試行錯誤してきました。
今回は、「心を強くしたい」と願う人に向けて、心の強さの一つの考え、「レジリエンス」と、強い心を鍛える方法について解説していきます。
心の強さ「レジリエンス」とは?
心の強さは、心理学では、「レジリエンス」という言葉に置き換えられます。
レジリエンスの定義を見てみましょう。
レジリエンス(resilience)
「回復力」や「弾力性」「反発力」などの意味を持つ言葉。
心理学の世界でも使われる。
ここでは、「ストレッサーにより心が凹んだときに、元に戻そうとする力」と定義する。
理解を深めるために、物理学の「反発力」に置き換えて考えてみます。
「反発力」は、「物体が他の物体により力を加えられたときに押し戻そうとする力」のこと。
たとえば、低反発布団を手のひらで押すと、手のひらのあとがつきますが、そのあとその形のままとどまるのではなく、徐々に元の平らな布団に戻っていきますよね。
このときに働いているのが「反発力」です。
反発力の強さは、「物体や表面の素材」と、「加えられる力」によって変わります。
たとえば、水筒は押されても変形しないですが、ペットボトルは押されると変形します。
また、ペットボトルが変形するかどうかは、加える指の力によっても変わりますよね。
強く押せば凹んだままになりますが、軽く押すだけであればすぐに元の形に戻ります。
これを心に当てはめてみると…
物体や表面の固さ(素材):心の強さ
加えられる力:ストレッサーの強度
ただ、心は、水筒のように全く影響を受けない固い素材になることは難しく、固い素材になることによる影響も大きいです。
一方で、粘土のように柔らかすぎても、凹んだまま元に戻れなくなります。
目指すべき状態は、凹んでも立ち直ることができるしなやかな心を作ることです。
「凹んでも跳ね返すことのできる心」をつくることで、ストレッサーの強度がちがっても立ち直ることができるようになります。
心の強さ「レジリエンス」の鍛え方
それでは、「凹んでも跳ね返すことのできる心」を作るためにはどうしたら良いのでしょうか?
レジリエンスの鍛え方にはいろいろな視点があります。
レジリエンス介入には次の5つの要素を含める必要があることを示唆している:1つ目は,反応性と衝動性を認識して管理するための感情制御レーニング。2つ目は,思考プロセスを再構成し,前向きな感情を高めるための認知行動アプローチ。3つ目は,保護行動を高めるための運動,栄養,睡眠,およびリラクゼーションに関する身体的健康の条件。4つ目は,保護因子を増やすために家族,仲間,メンターとのつながりを築くための社会的支援。5つ目は,マインドフルネスベースのストレス低減(mindfulness-based stress reduction)などの神経生物学的要素。
感情をコントロールすること、柔軟な考え方を身につけること、健康を保つこと、人とのつながりを大切にすること、ストレスを減らすこと。
これらが、レジリエンスを鍛えるための方法です。
感情をコントロールする
感情をコントロールする方法はいろいろあります。
アンガーマネジメント、リフレーミング、コントロールフォーカスなど。
アンガーマネジメントは自分の怒りの性質に気づき、怒る・怒らないを管理できるようになるための方法です。
リフレーミングは、物事を色んな角度で見れるようになることで感情の揺れを小さくする方法。
コントロールフォーカスは、自分が変えられないことには目を向けず、変えられる部分を変えることでイライラモヤモヤを減らす方法です。
これらの心理学的アプローチを活用するのも良いですし、まずは、自分が「どんな感情になりやすいのか?」に気づき、その感情を生み出さない方法、その感情になったときの戦い方、ケアの仕方を考えてみることもおすすめです。
柔軟な考え方を身につける
柔軟な考え方を身につけるためには、あたりまえですが、色んな考え方を知る必要があります。
「世の中には自分と違う考え方をする人もいるんだな」と気づくことが最初の一歩。
そこに気づけたら、「じゃあ、他の人だったらどう考えるんだろう?」と考えていく練習をしていきましょう。
色んな考え方を知るためには、人に聞くのも良いですし、漫画やドラマなどのエンターテインメントに触れたり、本を読んだりするのも効果的です。
そうして自分の中に「色んな場面の考え方のストック」を増やしていくと、ひとつの考え方に固執することなく、「そういえばこういう考え方もできるよな」と徐々に柔軟に捉えられるようになっていきます。
ちなみに、私もかなり一つの考え方に固執するタイプでしたが(今もその感じは残っています)、意識的に色んな考え方をしようと思うことで、大分生きやすくなってきました。ただ、一朝一夕で変わるものではなく、徐々にグラデーションで変わっていくものなので、あきらめずにトレーニングだと思って続けることが大切です。
健康を保つ
健康を保つのは、非常にシンプルで、睡眠・食事・運動をとにかくしっかりやる、守ることが大切です。
睡眠は、厚生労働省の睡眠指針によると、「6~8時間」の間でとると良いとされています。
成人においては、おおよそ6〜8時間が適正な睡眠時間と考えられ、1日の睡眠時間が少なくとも6時間以上確保できるように努めることが推奨されます。
ただし、人によって適切な睡眠時間は異なるため、自分が一番すっきりとしていられる睡眠時間を確保することが大切です。6~10時間の範囲であれば、適切な範疇と言えるようですね。
食事はバランスよくとること、適度な運動ももちろん大切です。
食事バランスガイドを参考に、自分に必要なエネルギーや栄養素を確認しながらバランスよく食べましょう。
運動については、65歳未満の成人の場合、厚生労働省の指針(健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(案))によると、1日8000歩以上歩くこと、息が弾み汗をかく程度の運動を週に60分以上、筋トレを週2~3日行うことが推奨されています。
人とのつながりを大切にする
人とのつながりについては、リアルなつながりでも、フィクションのつながりでもOKです。
公認心理士の伊藤絵美さんが、「セルフケアの道具箱」という本で、人とのつながりについて解説してくれています。
重要なのは、今、誰かに頼ることだけでなく、「頼れる人を探す」「心の中で誰かを思い浮かべる」「人間じゃなくてもいいから誰かと一緒にいる」ということでも、それは心理学的には確かに「誰かとつながる」ことになる、ということです。少なくとも「心をひとりにしない」ということです。
引用元:セルフケアの道具箱 伊藤絵美 2024.2.10 19版 晶文社
「信頼できる人に相談する」だけでなく、「推しに触れる」「昔の人とのかかわりを思い出す」「好きな人を思い浮かべる」「音楽を聴く」「アニメを見る」「映画やドラマを見る」「チャットをする」ことも、人とのつながりになります。
ストレスを減らす
ストレスを減らすための方法もいろいろあります。
物理的にストレッサーを失くす方法、ストレッサーをストレッサーとして認識しないように考え方を変える方法などです。
物理的にストレッサーを失くせるのであれば、一番効果的です。
たとえば、家族がイライラしていて自分にも影響があるのであれば、部屋を出るとか。
ストレッサーをストレッサーとして認識しないためには、上でもお伝えしたように時間はかかりますが、色んな考え方を取り入れていくことが大切ですが、他にも、行動を変えることで変わっていくこともあります。
たとえば、誰かに感謝をしたり良いところを見つけたりすることで、自分の考え方が変わっていく、ということがあります。
ストレッサーに触れたら、すぐに運動をする、歌を歌うのも、おすすめです。
まとめ
今回は、心の強さ「レジリエンス」と心を強くする方法を解説していきました。
日々生活を送る中で、人間関係や環境、気候、社会など色んなストレスが私たちに降りかかっています。
そんな中でも、自分の軸をぶらさずにいられるよう、レジリエンスを鍛えて心を強くしておくことは、自分の身を守るために大切なことなのではないかと思います。
この記事が、あなたの心を強くする一助になっていれば幸いです。