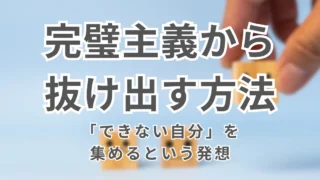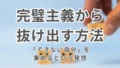完璧主義を手放すためには、
「手放した方が良い」と心から納得することが必要です。
この記事では完璧主義には精神疾患のリスクがあることを知り、手放した方が良いと納得するための情報をお伝えしています。

完璧主義から離れられない人の
手放すきっかけとなりますように。
完璧主義のリスク

完璧主義のリスクは、メンタルを壊す可能性があることと、生きづらさを生むことです。
メンタルを壊す可能性
私は精神疾患を抱えた方と接する機会の多い仕事をしていますが、
うつ病や双極性障害、統合失調症と診断を受けている人の多くは、完璧主義的傾向があるように感じています。
完璧主義(perfectionism)の精神的健康への影響について多くの研究(e.g., Chang, Watkins, &Banks, 2004; Fairburn, Shafran, & Cooper, 1999; Hewitt, Flett, Sherry, Habke, Parkin, Lam,McMurtry, Ediger, Fairlie, & Stein, 2003)がなされ、完璧主義と抑うつ、不安、強迫症状、摂食障害などのさまざまな精神的不適応との関係が指摘されている。
完璧主義の適応的構成要素と精神的健康の関係(2010)
実際、多くの研究で、
【自分の実力以上の理想を追い求めて達成不可能な高い目標を設定する完璧主義】が、生きづらさや精神疾患につながる可能性があると報告されています。
不適応な完璧主義と向き合わないままでいると、いつか心を壊してしまうかもしれない。
これが完璧主義の最大のリスクではないかと思います。
生きづらさにもつながる
完璧主義は生きづらさにもつながることがあります。

完璧主義が強すぎることが原因で
生きづらさを感じている人をご紹介します。
※個人が特定されないように一部改変しています
自分をチクチク攻撃しつづけるAさん
普通の設定が人より高いAさん
【入社1週間で社員全員の名前を覚えないといけない】
自分なりに一生懸命がんばっても全員の名前を覚えることは難しく、
できない自分を毎日責め続けて自分を傷つける日々を繰り返しています。
いつもイライラ。ストレスが積もっていくBさん
Bさんは自分が完璧に守っているルールを守ってくれない人に対していらだちを感じる傾向があります。
書類の書き方を知らない上司にイラっとしたり、誤字脱字のダブルチェックをしない後輩にムカついたり。
自分の中のルールが守られないことにストレスが積もっていきます。
頑張りすぎて毎日クタクタなCさん
Cさんは頑張りすぎていることに気づくのが苦手です。
期日が同じ仕事をいくつか抱えていても、「大丈夫。できるできる。」と、やりきってしまいます。やり切った後はいつも強い疲労感におそわれます。
また同じような場面があっても「できるできる」「大丈夫」と引き受けてしまって常に疲労が絶えません。
完璧主義がメンタルを壊す仕組み
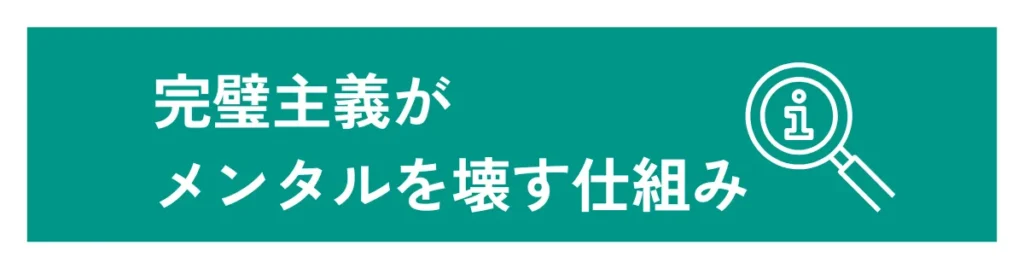
完璧主義がメンタルを壊すのは、完璧主義がストレスを生み出しやすく、ストレスは心に悪影響を与える可能性があるためです。
完璧主義はストレスを生み出す
ストレスは、自分の力で簡単に対応できない出来事に遭遇したときに生まれます。
完璧主義は、【完全無欠で失敗のないことを目指す考え】ですが、人が完全無欠で失敗なくすることはとても難しいです。
そのため、完璧主義の人は常に「簡単に対応できない難しい課題に向き合っている状態」になります。
つまり、常に「自分の力で簡単に対応できない出来事に遭遇している」状況となり、いつもストレスを生み出しているといえます。
ストレスは心・体に影響を与える
ストレスが脳や体に影響を与えることはよく知られています。
この影響のことをストレッサーと呼び、心理面・行動面・身体面にあらゆる反応が現れます。
文部科学省 第2章 心のケア 各論 1 心のケアの基本
⑴心理面の反応
情緒的反応として、不安、イライラ、恐怖、落ち込み、緊張、怒り、罪悪感、感情鈍麻、孤独感、疎外感、無気力などの感情が現れる。
心理的機能の変化として、集中困難、思考力低下、短期記憶喪失、判断・決断力低下などの障害が現れる。
⑵行動面の反応
心理面の反応は、行動面の変化としても現れる。
怒りの爆発、けんかなどの攻撃的行動、過激な行動、泣く、引きこもり、孤立、拒食・過食、幼児返り、チック、吃音、ストレス場面からの回避行動などが現れる。
⑶身体面の反応
動悸、異常な発熱、頭痛、腹痛、疲労感、食欲の減退、嘔吐、下痢、のぼせ、めまい、しびれ、睡眠障害、悪寒による震えなど、全身にわたる症状が現れる。
ストレス反応が長引くと精神疾患になる可能性がある
ストレス反応が続くとうつ症状が生まれてくると言われています。
ストレス反応が慢性化すると、まず活気が低下して、元気がなくなってきます。この状態が解消されずに慢性化すると、イライラや不安感を覚えるようになります。そして最終的には気分が落ち込んだり、ものごとがおっくうになるなど、いわゆる「うつ」の状態に近づいていきます。
2 ストレスからくる病(こころの耳)
ストレスにつながりやすい完璧主義の考えを続けていると、ストレス反応が慢性化して結果的にメンタルを壊す可能性があることが分かります。
精神疾患の日常生活への影響

仕事やプライベートを通じてたくさんの精神疾患がある人と接する中、
私が完璧主義を手放した方が良いと納得できたのは、精神疾患が日常生活に大きな影響を与えると肌で感じたことが大きいです。
そのため、ここではうつ病を例に精神疾患が日常生活に及ぼす影響をお伝えしていきます。
うつ病の症状
うつ病は、脳のエネルギーが足りなくなり、心や体に様々な影響を及ぼす病気です。
うつ病は、一言で説明するのはたいへん難しい病気ですが、脳のエネルギーが欠乏した状態です。それによって憂うつな気分やさまざまな意欲(食欲、睡眠欲、性欲など)の低下といった心理的症状が続くだけでなく、さまざまな身体的な自覚症状を伴うことも珍しくありません。
1 うつ病とは(こころの耳)
つまり、エネルギーの欠乏により、脳というシステム全体のトラブルが生じてしまっている状態と考えることができます。
うつ病の症状は人それぞれです。
- 体が重くて動かない
- 頭がうまく働かない
- 強い絶望感に襲われる
- 何に対しても喜びや楽しみを感じられない
- ずっと気分が晴れない
- いつも不安や焦りを感じている
参考:マンガでわかる!うつの人が見ている世界 文響社(2023.8)
1 うつ病とは(こころの耳)
これらの症状は自分でコントロールすることが難しいものです。

自分で自分の行動・気持ちを
コントロールできない状況は
とてもしんどいですよね。
私が出会ったうつ病の人
起き上がれないAさん
起きようとしても起き上がれない。
仕事だし起きなきゃいけないと分かっているけどなぜか体を起こせない。
まるで体になまりがついて重たくなっているみたい。
涙が止まらないBさん
悲しくないのに涙が止まらない。
寝ているときも人と話しているときも自然に涙が出てくる。
止めたいけど気持ちをうまくコントロールできない。
感覚過敏になったCさん
普段は何ともなかったにおい、音がとても辛く感じる。
満員電車に乗れなくなった。
耳栓やマスクで対策してもダメだ。
※個人が特定されないように一部改変しています
精神疾患を発症すると、発症前あたりまえにできていたことができなくなります。
何か対策を打ってすぐに回復する病気でもありません。
私が出会ったうつ病の人たちは、「早くうつから抜け出したい」と話す人たちばかりでした。
服薬をして生活リズムを整えても、なかなか抜け出せない様子をたくさん見てきました。
- 休職しなければならなくなり、家事や子育てもやりたいことの半分以下しかできない。
- 何を見ても心が晴れずずっと憂鬱な気持ちを抱えている。うつ抜けするための方法も分からない。
想像しているよりもずっと長く重たく、日常生活に影響が出るのと感じています。
だからこそ、精神疾患になることは予防した方が良いというのが私の考えです。
完璧主義を手放した方が良い理由

ここまでの話から、あらためて完璧主義を手放した方が良い理由をまとめます。
精神疾患にならないため
私が思う完璧主義を手放した方が良い理由は「精神疾患にならないため」これだけです。
不適応な完璧主義は生きづらさやストレスにつながる可能性が高く、ストレスは精神疾患のリスクを高めます。
精神疾患は日常生活に大きな影響が出る病気で、回復には時間も労力も精神力もかかります。
精神疾患になるリスクを高めないために、完璧主義は手放した方が良いと私は納得しています。
おわりに
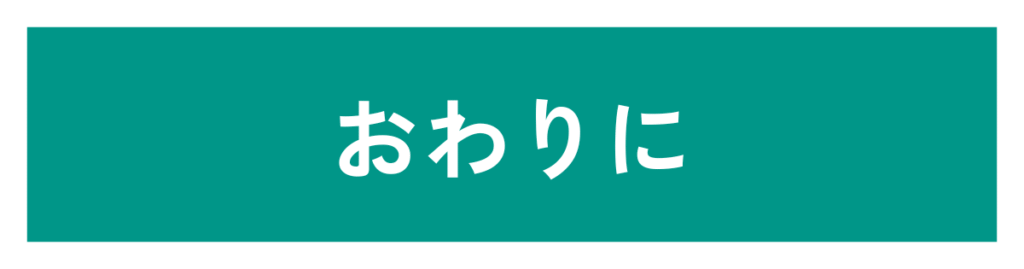
今回は完璧主義のマイナス側面にフォーカスして色々と調べ考えました。
完璧主義でいることで自分が楽になっている側面もあってなかなか手放せないことがあると思います。
私が完璧主義を手放す作業に取り掛かるとき、「本当に変えた方が良いんだ」と心の底から納得することが必要でした。

このブログが納得のヒントと
なっていましたら幸いです。