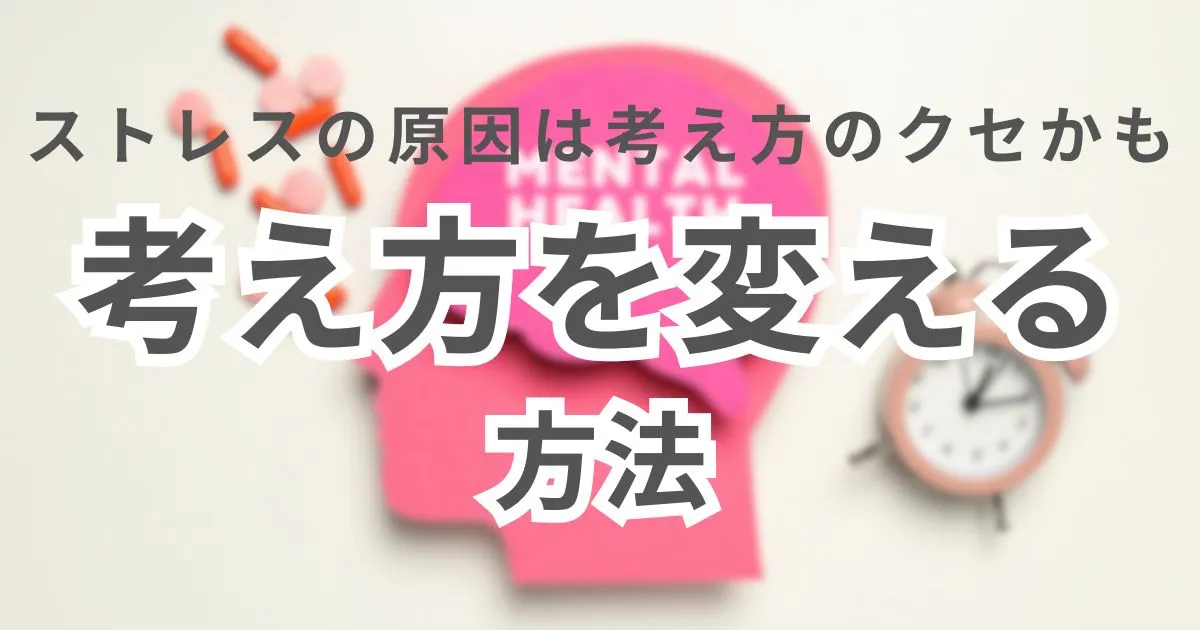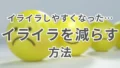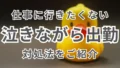- 考え方のクセってどういうものなのか知りたい
- 考え方のクセを知る方法って?
- 考え方を変えるにはどうしたらいい?
ストレスを感じている人の頭の中には「考え方のクセ」が潜んでいるかもしれません。
考え方のクセにゆがみがあると、物事をすべてマイナスに受け取ってしまったり、悲観的に考えてしまったりして、ストレスがたまっていく可能性があります。
この記事では、まず考え方のクセを知るところからはじめていきます。そのあと、変えていく方法をご紹介していきます。

日々のストレスを減らすヒントを見つけていただけたらうれしいです!
考え方のクセとは?
日常で何気なく繰り返している思考パターンのこと
世の中にはいろんな情報があふれていますが、その情報をどう受け取るかは人それぞれの考え方によります。
同じ出来事でも、マイナスに受け取る人もいれば、ポジティブに解釈する人もいます。
【上司から「Aさんはいつも早く来ていてすごいね」と言われた】出来事に対して、
「ほめられた!明日からも早く来て頑張ろう」と思う人もいれば、
「え、早く来すぎてたかな…もしかしたら迷惑だったのかもしれない…明日からは遅く来るようにしよう」と捉える人もいます。
上司の本音がどちらかは分かりませんが、言葉そのままの意味だった場合、マイナスに捉えている人は自分の解釈で自分のことを傷つけてしまっていることになるのです。
こうした考え方のクセについては、アーロン・ベックが、「認知のゆがみ」として基本的な理論を提唱しています。
0or100思考

物事を0か100のどちらかしかないと極端に捉える考え方です。
白黒思考と呼ばれたり、全か無か思考と呼ばれたりもします。
- ミスを指摘された。もう会社を辞めるしか道はない
- 大学に行くなら東大じゃないと何も意味がない
- 地元に帰るなら恋人とは別れるしかない
- 友だちとの関係性は「縁を切る」か「仲良しを続けるか」の選択肢しかない
- あいまいな状況があるとはっきりさせたくなる
このように、1~99や、グレーのような、どっちつかずな考えが思い浮かびづらい傾向があります。
どっちつかずな考え方をしようとすると、モヤモヤしたりどっちかに振り切ってハッキリさせたい!という気持ちが強くなるのも、0or100思考のあるある。
ふり幅の大きいふたつの選択肢にもとづいて行動するため、人からは「極端な人だなー」と見られる可能性が高いです。
過度の一般化

過度の一般化は、ある一部の出来事を、他のことすべてにも当てはめてしまう考え方です。
- あの人は誤字脱字が多い。仕事ができない人だ。
- 道を間違えて遅刻した。自分は本当にだめなやつだ。
- 約束を破られた。この先どんなことをお願いしても守ってはくれないだろう。
- 学校の友だちに仲間外れにされた。他の場所に行ってもどうせ友達なんてできない。
このように、「その時だけ」や「その部分だけ」「その環境でだけ」など、限定的に起こった出来事でも、「この先起こることや関連することも同じような結果になる」と考える傾向です。
この考えがあると、人から見るとなんてことのない小さな出来事も大きくとらえて、必要以上に傷ついてしまうかもしれません。
ラベリング

ラベリングは、「Aな人はBだ」「このカテゴリ―の人は〇〇な傾向がある」など、ラベルをぺたぺた貼るように自分や人を分類分けする考え方のクセです。
- 福祉関係の仕事をしている人はやさしいはずだ
- 男性は人の話を聞くのが苦手
- 時間にルーズな人はみんな不規則な生活を送ってる
- 母親は自分のことを分かってくれる存在だ
- 友人のAちゃんは明るくて楽観的な人だ
こんな風に、人や自分を、「こんな行動をする人」「こんな特徴がある人」と仕分けしていきます。
無意識の内にラベリングしていることも多く、それが常識となっている場合もありますが、いきすぎると相手や自分と向き合うことが難しくなる可能性があります。
また、その人の本質が貼っていたラベルと全然違うと分かったときに、ショックを受け、裏切られたような気持ちになるかもしれません。
自分に対しても、ラベリングした自分と違う自分を見つけたときになかなか受け入れられない可能性があります。

ラベルだけでその人のことを見ないように、いつでもラベルをはがせる準備をしておくことが大切です。
占い思考

根拠なく悪い出来事が起こると予測して、過度な不安や緊張につながる考え方です。
- 明日恋人に振られる予感がする。もし振られたら立ち直れない。どうしよう。
- 面接で噛んでしまうかもしれない。噛んだら、面接官に呆れた顔をされてしまうだろう。どうしたらいいんだろう…。
- きっと次の異動先でも上司に嫌われる。どこに行ってもうまくいかない。もし、上司に嫌われたら今度は辞めさせられるかもしれない。どうにかして好かれるようにふるまわないといけないけどうまくできるかな…。
まだ起きていない先々のことを予測しすぎて不安になってしまうという方は案外多いのではないかと思います。
自分でも無駄なことをしていると分かっていても、なぜかやめられず、延々と「ああなったらどうしよう」「もしこうなった場合はどう対処したらいいんだろう」と考え続けてしまうのではないでしょうか。
さらに、予測が当たった経験が多ければ、より考える頻度が多くなるでしょう。

こうなったときは、割り切ることと、考えを捨てる勇気が大切です。
「未来は何が起こるか分からない。今考えても仕方がない。何も変わらない。今私にできることは何もない。寝る!」
未来の自分がどんな気持ちになるかは、その時にならないと分かりません。
他者のことであればなおさらそうです。
「まだ起きていないことを考えても何も変わらない」と強く意識すると、結構気持ちが楽になりますよ。
拡大解釈・過小評価

出来事や状況を、過度に大きく、もしくは過度に小さく見積もる考え方です。
事実を客観的に見たときにくだる評価と、自己評価にギャップがあることが多いです。
- 午後から雨予報なのに洗濯物を取り込んでくるのを忘れてしまった。私は本当に何もできなくてだめな人間…。(拡大解釈)
- プレゼンの資料が分かりやすいと褒められた。こんなの誰にでもできるのだから、ほめられて舞い上がっちゃだめだ。もっと上を目指さないと。(過小評価)
誰かがこの考えを聞いたら「そこまで!?」「考えすぎ!」と言うでしょう。
本人の状況は、客観的に見たらそこまでの出来事じゃないと認識していても思考から離れられなくなっているパターンと、客観視できないほど考え方のクセに囚われているパターンがあります。
〇〇べき思考

〇〇べき思考は、その名の通り、「こうするべき」「こうしないといけない」と考える癖のことです。
- 恋人なら毎日連絡すべき
- 遅刻したらまず謝罪をすべき
- 待ち合わせ場所には10分前に着いておくべき
- 作成した資料は3回は読み直すべき
「〇〇べき」と考える要素が多いと、そこから外れた行動を自分や誰かがしたときに怒りを感じてしまうことがあります。
自分をしばり、相手へ期待することになるため、自分にがっかりしたり誰かにマイナスな感情を抱いたりすることも多くなっていくでしょう。
感情的決めつけ

感情的決めつけとは、なんでも感情に基づいて物事を判断したり行動したりすることです。
- 恋人といるとモヤモヤする。モヤモヤがあるなら別れた方が良い。
- 最近友だちが構ってくれなくて寂しい。寂しさがあるんだから家に行ってみよう。
- 毎日職場でイライラしているってことは、私はこの仕事が合わないんだ。
- 彼氏にお皿洗いをしていないと注意された。自分もしていないことがあるくせにとイライラ。つい、「自分もやってないことあるじゃん」と強い口調で言ってしまった。
感情をうまくコントロールすることが難しく、感情を根拠に物事を判断したり行動したりします。
行動した後は、感情的になった自分に対して後悔することも多く、自己嫌悪に陥る人もいます。

感情を客観的に眺めたり、感情をコントロールする術(アンガーマネジメントなど)を身につけたり、そもそもその感情が生まれないように認知を変えるトレーニングをしたりすると楽になります。
自己関連付け

何か悪いことが起こったときに、自分のせいだと過度に思い込んでしまう考え方です。
- 何度か勤務姿勢に注意をしたことがある部下が退職することになった。自分が注意をしすぎたせいだ。
- 恋人の機嫌が悪くて口数が少ない。俺が気に障ることを何かしてしまったのかもしれない。
- 旦那が糖尿病になってしまった。私がもっとちゃんと栄養バランスを考えた料理を食べさせていればこんなことにならなかったのに。
このように、すべて「自分のせいで今の状況になった」と考えてしまいます。
実際は、部下が退職することになったのは家庭の事情かもしれないし、恋人の機嫌が悪いのは体調がすぐれないからで、旦那が糖尿病になったのは隠れてケーキをたくさん食べていたからかもしれません。
事実とはちがうところで不安になったり落ち込んだりして、自分自身を辛くさせてしまう考え方です。

事実を確かめて自分の思い込みが全然違うんだという経験を積んでいくと解消につながっていく可能性があります。
悲観的

なんでも悲観的に、マイナスに捉えてしまう考え方です。
- 一口ちょうだいと友だちに言ったら断られた。汚いと思われているのかも…。
- 新しく買った洋服の色をほめられた。普段はそんなことないのに、今回ほめられるってことは何か裏があるのかもしれない。
- タイピングが早いと言われた。打つ音がうるさかったってこと?
「ほめられる」という出来事は、ストレートに考えると嬉しいことだと思います。
でも、悲観的な考え方のくせがあると、素直にほめられたことを受け取ることが難しく、「何か裏があるのでは」「他に伝えたい意図があるのでは」と考えてしまいます。
また、お願いしたことを断られた場合も、そこにある事実は「断られた」だけで、相手が自分をどう思っているかまでは含まれていません。
でも、マイナスに捉えると、断られたことの背景に思いをはせてしまい、落ち込みにつながる可能性があります。

こうした悲観的な思考に陥ったときには、「本当にそうなの?」「そう言っていた?」「そこまで悲観的になることなのかな?」と自分に問いかけるトレーニングを積み重ねることもおすすめです。
心のフィルター

心に「悪い面だけが目に入る」フィルターをセットしている状態です。
「良い面」「悪い面」両面を持ち合わせた出来事があったときに、「良い面」はフィルターを通れず、「悪い面」だけがフィルターを通って認識してしまう考え方です。
- 上司から、「資料の作り方がすごく上手だね。あとは発表の練習回数を増やすともっとプレゼンがうまくなるよ」とアドバイスを受けた。プレゼンが下手なのに練習が足りなかった。もっとがんばらなきゃ…。
- 在宅ワークが開始された。在宅だとすぐに人に聞けないし、コミュニケーションの機会も減る。いいことなんてひとつもない。
- 恋人と付き合って1年記念日。前から旅行に行こうと計画を立てていた。2か月前に予約サイトを見ると、泊まりたかった旅館は予約で満席。彼はホテルでも良いというけど、ホテルだと雰囲気が全然違うし、料理だって部屋食じゃなくなる。デメリットしかない。
上の例を客観的に見てみると、上司からは「褒め1、指摘1」とバランスよく言われています。
また、在宅ワークはたしかに「コミュニケーションの機会が減る」デメリットはあるけれど、「通勤時間が減る」などのメリットも多いです。
旅館とホテルも、それぞれ特徴が違っていて、メリット・デメリットの両面があります。
でも、フィルターがかかっていると「メリット・デメリット」の「デメリット」の部分しか目に入らなかったり、「褒め・指摘」の「指摘」にしか着目できなかったりします。
フィルターは自分の体調やその日の気分によってセットされるかされないかが違う場合があるので、できるだけ体調を整えておくことも大切です。
考え方のクセを変えるためにやってみて効果があった方法
考え方のクセ(認知のゆがみ)を変える方法は、色々あります。
心理士の先生方がYouTubeや本でまとめてくれていたり、たくさんのブログでも紹介されています。
今回は、その中で私が実践してみて良かった方法、実践しやすかったやり方、独自にやってみていることをご紹介していきます。
「でも」「だって」を「あー」「へー」に変える!
「でも」や「だって」は、考え方のクセが出てくるサイン。要注意です!
考え方のクセが強い人は、自動的に頭に「でも」や「だって」が思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。
物事をポジティブに解釈する人もいればマイナスに解釈する人もいる
→「でも」、それって当たり前じゃない?(過度の一般化)
→「だって」、マイナスにしか考えられないし(0or100思考)
→「でも」、ポジティブだけじゃなくて幅を持って考えるべきでしょ(べき思考)
「でも」や「だって」を言いそうになったら、ぐぐっとこらえてみましょう。
そして、代わりに、「たしかにそうかもしれない」「そういう考えもある」と一度飲み込んでみます。
慣れない内は喉につっかえるような感じがして、うまく咀嚼できないと思います。
上の2つの言葉が難しければ、「あー」とか「へー」でも良いです。言葉をそのまま受け止めるための時間を作りましょう。
「あの人だったらどう考えるかな?」という視点で考える
物事を別の視点から捉えなおすことを「リフレーミング」と呼びます。
リフレーミングの手法(考え方)はたくさんありますが、その中でも、「自分が好きな他者の力を借りる方法」が私はおすすめです。
客観的な視点に立てますし、考えているときも嫌な気持ちにならないから、取り組みやすいです。
友だちとの関係性は「縁を切る」か「仲良しを続けるか」の選択肢しかない
→推しの子のアイだったらどう考えるかな?
→「一緒にいたくない時期なら、一緒にいなくていいんだよ!また仲良くなれるときが来るさ!」って考えるかも
相手はだれでも良いです。
推しのキャラクターでもアイドルでも、家族や友人、恋人・パートナー、先生など身近な人でもOKです。だれかを自分に憑依させることにより、自分にはない新たな視点を獲得しやすくなりますよ。
小さな「ありがとう」をたくさん見つけて許容範囲を増やす
小さな「ありがとう」をたくさん見つけると、自分の許容範囲を広げることができます。
なぜ「ありがとう」を見つけると許容範囲が広がるのかを考えたことがあるので共有しますね。
まず、【0or100思考】や【〇〇べき思考】が強くでる考え方のクセを持っている人は、「まあいっか」とあいまいに考えられる幅を広げることで、ずいぶんと楽になるはずです。
「まあいっか」と思える範囲を広げるためには、相手への期待値を下げる必要があります。
そして、期待値を下げるためには、許せる範囲を広げなければいけません。
許せる範囲を広げるには、自分と相手の違いを認めることが必要です。
自分と相手の違いを認識する手段の一つが、「ありがとう」を見つけることなんだと思います。
見つけた「ありがとう」の背景には、「相手が考えてしてくれたこと」があるはずです。
そこには、自分とは違う相手の価値観が隠れています。
その価値観に対して「ありがとう」と思うことで、自分と相手の違いを認めることにもつながり、結果的に期待値が下がっていくのではないでしょうか。
考え方のクセが出ていると気づいたら違うところに意識を向ける
誰かと一緒にいるとき、言われたことに対してモヤッとしたりイラっとしたりすることがあります。
ひとりでいるときも、ふと昔の出来事を思い出して悲しくなることもあります。
こんなとき、「ああ、考え方のクセが出ているな」と気づけたら、意識を違うところに向けるのがおすすめです。
道を歩いているのであれば、お店の看板の文字を見て「赤字で中華料理…。店の名前は、龍…。」と目に見えているものを頭の中で唱えてみたり、「暑い。風が少しある。歩くスピードが落ちている。」と身体的に感じていることを意識したりします。
意識を違うところに向けられると、考え方のクセに飲み込まれずに済みます。
いつの間にかイライラにつながる考えや、悲しくなった気持ちが遠くのぼんやりしたものになっていて思い出せなくなったら、成功の証です。
仕事であれば、目的に沿って「本当に必要な考えか?」でシステマティックに仕分けする
仕事で考え方のクセが出る場面が多いのであれば、システマティックに考えることもおすすめです。
プライベートでは答えがなくいつまでも考えられることが多いですが、仕事の場合は目的が明確でその目的に沿って物事を判断できるものが多いです。
そのため、物事を目的に沿っているか・沿っていないかで仕分けすることで考え方のクセを取り払って物事を見ることができます。
営業さんが使いやすい資料をできるだけ早く作ることが目的の場合
【考え方のクセ(〇〇べき思考)】
後輩が作る資料はいつも誤字脱字があってイライラする。毎回私に最終確認をさせてきて、なんなんだろう…。誤字脱字は自分で直すべきだし、誤字脱字をする頻度が多いならそれなりに自分の力で対処法を考えるべきだと思う。今回は自分で確かめてもらいたい。
【目的に沿って考えてみる】
「誤字脱字を見つけることが難しい後輩」に自分で確かめるようにお願いすることで余計に時間がかかってしまうかもしれない。それであれば、後輩には一次チェックをしてもらい、自分が最終確認をする方が結果的に質が高い資料をはやく作成することができる。
こんな感じで、仕事を効率的に合理的に進めるために必要な方向を選ぶことは、意外と「〇〇べき思考」が強い人には向いているのではないかと思います。
自分の中で論理的に納得できると、過剰な「〇〇べき」を抑えることができるので、ぜひ試してみてほしい方法です。
客観的に見つめる
考え方のクセに陥ったときには、「自分から考えを引き離す」ことも効果があります。
考え方のクセに陥ると、どうしても主観的でしか物事を見れなくなるし、視野がぐーっと狭くなって「それしかないんだ!」「絶対そうだ!」となってしまいがちです。
客観的に今自分が考えていることを見ると、「なんだそんな大したことじゃないじゃん」「え、考えすぎじゃない?」「なんでこんなくだらないこと考えてたんだろう」と一歩引いて冷静になることができます。
客観的に見る方法はいくつかあるようですが、私が試して効果を感じているのはこんな方法です。
- 自分が考えていることを紙に書き出して眺めてみる
- 主語を自分以外の誰かにする
特に、書き出す方法は私には合っていました。
書き出すことでデトックス効果も感じられますし、書き出した内容を眺めると本当に「まあいっか」と思えてくるものです。
人に話して客観的な意見を聞く、頭の中で自分に話しかける他人をつくるなんて方法も効果があったと聞いたことがあります。
色んな方法を試して、俯瞰で自分を見つめられるやり方を見つけられると少し楽になるはずです。
一番大切なのは、毎日積み重ねること
変わりたいと思ったとき、すぐに結果がほしくなる方もいるのではないでしょうか。
やるからにはすぐに効果を実感したい、それは当然のことだと思います。
でも、残念ながら考え方のクセは一朝一夕で変えられるものではないと私は考えています。
昔、箸の持ち方を指摘されて正しい持ち方にするために毎日トレーニングしたことがありましたが、自分で意識せずに正しい持ち方ができるようになったのは半年後でした。
体の癖を変えるのと同じで、心の癖も、毎日意識をして、少しずつ自分の心に慣らしていき、いつの間にか自分の本当の心の一部になっているという感じで変わっていくように思います。
長期的な目で考え方のクセを変えようと考える方へ向けて、私が実践しているステップをご紹介します。
①自分が陥りやすい考え方のクセを知る
②考え方を変える方法を知る
③考え方のクセが出ていた過去の経験を思い出して、その時どうすればよかったか考える
④考え方のクセが出たときに②や③で知った方法を試してみる
どれも少し大変な作業ですが、積み重ねることで自分の心の変化を感じられるはずです。
今回ご紹介した方法の中で取り入れやすいものから、ぜひ生活の中で試してみていただけるとうれしいです。
まとめ
考え方のクセが強くて辛く感じている人も多いのではないかと思い、今回の記事を執筆しました。
私自身、「白黒思考」や「〇〇べき」思考の考え方が強く、自分や人に理想を押し付けて人間関係がうまくいかなかったり自分のことが嫌になったりした経験があります。正直、今もそうです。
それでも、毎日少しずつ考え方を変えることを意識することを積み重ねることで、昔より大分やわらかい考え方になってきたように感じています。毎日意識をすること、何かひとつでもやってみることが、自分を変える第一歩になると信じています。
ここまでの内容をまとめておきます。
【考え方のクセ】
【考え方を変える方法】
この記事が、みなさんが考え方のクセから抜け出せる一助となっていたらうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
記事執筆にあたり、参考にさせていただきました。
- 人見ルミ 働く人のためのメンタルコントロール 株式会社あさ出版 2023年9月
- 大野裕 心が晴れるノート 株式会社創元社 2003年3月
- 鈴木裕介 メンタル・クエスト 株式会社大和出版 2020年4月