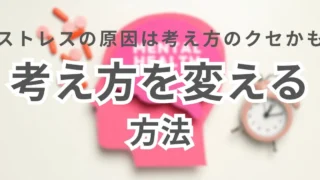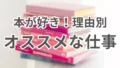社会人になってから完璧主義傾向に気づき苦しめられてきましたが、数年かけて抜け出しつつあります。
あらためて完璧主義の定義とあるあるについて調べてまとめてみました。

戦いたいものがあるのならば
まずは敵を知るところから。
ということで、完璧主義から抜け出したい方の足掛かりとなりましたら幸いです。
完璧主義の定義

完璧は、
- 完全無欠ですぐれていること。
- 瑕(すき)のない璧(たま、宝玉)の意から。
「主義」は、
- 常に守る考え方や行動の方針
参照:現代国語例解辞典【第四版】(2008)
このふたつの言葉の意味から、完璧主義は次のように定義できます。
「完全無欠で失敗のないことが何より大切」という考えが思考の軸や行動の方針となっている様子
2種類の完璧主義

エネルギーを生み出す完璧主義と、ストレスにつながる完璧主義があります。
完璧主義が不適応的構成要素と適応的構成要素を持つことは、古くは Adler により述べられている(Enns & Cox, 2002)。Adler
完璧主義の適応的構成要素と精神的健康の関係(2010)
エネルギーを生み出す完璧主義
現実的な目標を設定し、その達成のために計画的に着実に行動するタイプです。
- 計画性がある
- 能力の限界を認めている
- ルールを守る
このような特徴があります。
入社1か月では仕事の大体の流れを把握したい。そのために1日ずつ取り組むことを決めてひとつずつ進めていこう。
前向きな気持ちに満ちている、やる気がある、自分を肯定できるなどの傾向があるようです。
ストレスにつながる完璧主義
自分の能力をはるかに超えた目標を設定するタイプです。
- 目標が高すぎる
- 自信がない
- 失敗を極端におそれる
このような特徴があります。
入社1か月ですべての仕事でミスがないようにしないと。それができない自分はダメな人間。
常に焦燥感に追われている、不安が強い、達成できない自分を否定するなどの傾向が考えられます。
こうした不適応的構成要素をもつ完璧主義者は、抑うつ症状の経験がある人も多いことが報告されています。
不不適応的完璧主義群においては、適応的完璧主義群および完璧主義でない群に比較して、抑うつ症状を多く経験していた。
完璧主義の適応的構成要素と精神的健康の関係(2010)
抜け出したい・変えたい完璧主義は、ここでいう不適応的完璧主義に当てはまりそうです。
完璧主義メリット・デメリット

2種類の完璧主義があることから、完璧主義=悪いものとは言えないことが分かりました。
完璧主義のメリット
- いきいき、楽しい、キラキラなどのプラスの感情が生まれやすい
- 成長していける
- 規則を守れる
- 自己効力感、自己肯定感を高められる

エネルギーを生み出す完璧主義の場合、
達成できる目標を設定してひとつずつクリアしていくため、
自己効力感(自分の「できる」を信じる力)を高められると考えられます。
完璧主義のデメリット
- 不安、焦燥感、心が暗い・重いなどマイナスな感情が生まれやすい
- いつまでも成長していない感覚がつきまとう
- 過剰なルールが自分や他人を苦しめる
- 自己効力感、自己肯定感が低くなる

ストレスにつながる完璧主義では目標を非常に高く設定するため、
「達成できない自分」に触れる機会が多くなります。
そのため、自己効力感や自己肯定感が落ち込んでいくのでしょう。
ちなみに私もこのデメリットは経験があります。
勝手に高すぎる目標を設定して、ついひとりでキャパオーバーの作業を抱えてしまって自滅する、自滅した自分にがっかりする、結果自信を無くす…というひとり芝居…。
ストレスにつながる完璧主義あるある

- 失敗を人に見られることがこわい
- ちゃんとしないと、と思うことが多い
- ひとりで何でもやろうとする
- アレもコレもやらないといけないと不安になる
- 結果できないことが多く落ち込む
- 人に頼るのが下手・苦手
- 〇〇べき、~ねばならないが強い
- 自分ルールにしばられている

当てはまった人は
考え方をゆるめる練習をすると
楽になるはずです!
考え方を変えるのはすごく時間がかかりますし根気が必要です。自分と向き合わないといけないんですよね。
考え方の変え方はこちらのブログで詳しく解説しています。
完璧主義の人に多い2つの傾向
ここまで完璧主義の特徴や種類を学術的に見てきましたが、
実際に私が支援現場や身近な人を見ていて感じた傾向も合わせて紹介します。
これまで出会ってきた完璧主義的思考の人たちは2種類に分けられます。
- 理想が高い
- 否定されてきた経験が多い

※私自身と周りの人から考察した個人的見解です。
理想が高い
完璧な自分でいたい思いが強く、完璧でない自分を認められない人です。
- 私はちゃんとした人だから
- 失敗するなんてありえない
- 褒められ続けないと
- みんなよりできる人のはずだから
昔から人よりもできることが多かったりほめられた経験が多かったりする人が多いように思います。
失敗する自分を認められないため少しの失敗でも傷つきやすく自己否定につながりやすいです。
ちなみに私はこちらのタイプで、昔から理想の自分がいて、言葉と行動は絶対に一致していないといけないとか、嘘は絶対についてはいけないとか、色んな縛りを自分に課しがちです。
否定された経験が多い
失敗することで否定された経験が多くあり、完璧でいないと嫌われる・怒られると思っている人です。
- 普通これはできるよね?こんなこともできないの?と否定された経験が多い
- ちゃんとやりなさい、と怒られた経験が多い
- 他の人と比べてできていないことが多かった
- 失敗して冷たい目で見られることが多かった
他人から否定された経験が多いことで、「ちゃんとしないとここから排除される」と無意識に感じて「完璧にやらないと」という思いにつながっている人も多いように感じます。
ちなみに私が関わっている発達障害の診断を受けている人はこちらの経験をしている人が多いように感じています。
完璧主義の根本にある3つの願望
さらに深掘りすると、行動の背景には共通する“願望”が存在します。
その願望を理解すると、完璧主義と距離を取るヒントになります。
完璧主義を裏返すと、3つの願望が現れます。
- 状況の打破
- 不安の回避
- 理想の追及
状況の打破
今置かれている不幸せな状況から抜け出したい、という願いです。
この場合、完璧を目指すことが、不幸な状況を解決する解決策になっています。
たとえば、
子育てで子どもがよく幼稚園で喧嘩をしてしまう。優しい子に育ってほしいのにうまくいかない。もっとちゃんと伝えて人とのかかわり方を教えないと。
という考えがあるとします。
この背景には、「私の伝え方が足りないから子供が喧嘩をしている」という考えがあると考えられます。
今の「子供が喧嘩をしてしまう」状況を抜け出す解決策として、「私の伝え方をもっと良いものに変えてちゃんと教える」というものが挙がっています。
このように、「今の不幸せな状況を解決するには自分の行動をより良いものに変えるしかない、変えれば解決するはずだ」と過度な考えが行き過ぎて完璧主義になっているパターンです。
「完璧」が全てを解決してくれるという考え方です。
不安の回避
不安や焦りから逃げ出したい、という願いです。
完璧主義の人が抱えている不安は、「自分ができない人間となること」「人にできないと思われること」「失敗すること」「怒られること」「嫌われること」こんなところでしょうか。
「これらの状況になるかもしれない」という不安を落ち着かせるために、「そうならないための行動」として完璧を目指している場合があります。
つまり、完璧を目指すことが不安を落ち着かせる心の安定剤になっているのです。
たとえば、
「自分ですべて解決しないといけない」と思っている完璧主義の人の場合。
この背景には、「人に聞いたらそんなことも分からないのかと言われるかもしれない」という不安があるかもしれません。
この不安を回避するために、「全部自分で解決できるようになる」という完璧を目指して、たとえば自宅で勉強をしたり人よりも多く残業をしたりするかもしれません。
この勉強や残業が、「人に聞くこと」によって起こるかもしれない傷つく体験への不安に遭遇する可能性を下げているように感じられるのです。
「人一倍勉強をすれば、自分ですべて解決できるようになる。そうしたら、人に聞く必要もなくなって、人から分からない人と思われる危険もなくなる。だから勉強していれば大丈夫なんだ」というような形です。
不完全でいることで起きる可能性のある出来事に対して過度な不安があり、完璧を目指して努力を続けることでその不安を回避できると思い、安心感を得ている状態です。
理想の追及
理想の自分でいたい、という願いです。
「理想像の自分」がいて、それがイコール完璧になっているので、その理想に到達しようとして完璧主義になっているパターンです。
ちなみに、私はこの願いが一番強かったと感じています。
ロールモデルとしている人がいて、その人みたいに行動できない自分を認められず、そこに近づこうとしてもがいていました。
また、昔から褒められる経験が多かった人や、人よりもできることがあった人もこのパターンになりやすいです。
「できる(できていた)自分」がいるからこそ、そこから外れた自分のことは認められず、完璧でいないと落ち着かなったり、できていない自分にどうしても苛立ってしまったり。
また、褒められる経験が多いと、「褒められる自分でいないといけない」と無意識に感じている可能性もあります。
おわりに

不適応的完璧主義が強くなるとストレスや精神疾患につながる可能性も出てきます。

私たちが目指すべきゴールは
完璧主義をなくすことではなく、
エネルギーを生み出せる適応的完璧主義に
シフトすることなのかもしれません。
引き続き完璧主義との向き合い方を書いていきます。
このブログが完璧主義と向き合うきっかけになっていれば幸いです。